狐塚古墳

- [玄室部]横幅:2.7メートル、奥行き:5.7メートル、最高遺存高:2.0メートル
- [_道部]横幅:1.6メートル、遺存長:2.6メートル、最高遺存高:1.6メートル
この古墳については、古くからその存在が知られており、明治8年(1875)には発掘され、遺物も出土している。平部_南の「日向地誌」には、須恵器や勾玉、切子玉などが出土したことが記されている。
平成元年に実施した日南市内遺跡詳細分布調査でその存在は、確認されていたが、その性格や規模などは不明であった。平成6年2月〜11月には、本調査を実施し、調査の結果、この古墳は、横穴式石室を有する古墳時代終末期の日本の最南端に位置する古墳であることが判明した。残念なことに羨道部分や天井部分は、破壊や崩落のため築造当時の面影をみることはできなかった。平成12年5月には、墳形確認のため、遺存する墳丘の周辺にトレンチを設定して、調査を実施した。調査の結果、現地表下の攪乱が著しく墳形・規模を確認するにはいたらなかった。
しかしながら、平成6年(1994)に実施した本調査での出土品は、馬具や武具、勾玉や切子玉などの装飾品、須恵器など多種多様にわたる。特に金銅製装飾大刀、金銅製馬具・銅椀などは、通有の古墳からはほとんど出土することがない貴重な発見となった。また、横穴式石室の玄室規模では、宮崎県内最大のものと判明した。狐塚古墳では、出土した須恵器から、7世紀第1四半期末(620年前後頃)に最初の被葬者が、第3四半期初め(660年頃)までに最後の追葬を行ったものと推測される。
狐塚古墳をめぐる歴史的背景の解釈は、困難である。しかし、政治的身分を象徴する装飾大刀を被葬者が所有していたことから、ヤマト王権(大和朝廷)と密接に関わった新興地域勢力首長と想定することが妥当と推定される。いずれにしても、古墳時代終末期=飛鳥時代における南九州の政治的動向を理解する上で、きわめて重要な古墳と認められる。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 種類 | 古墳 |
| 文化財指定等 | 県指定 |
| 指定年月日 | 1937年9月12日 |
| 所在地(官報・文書等の記載) | 日南市大字風田字元弓場3649番地2 |
| 近隣集落・小字 | 風田 |
| 年代 | 原始・古代 |
| 関連文化財群 | 外 |
| 保存活用区域内 | 外 |
| 出典 | 日南市指定文化財一覧 (日向地誌)S-203 |
| 備考 | 海濱の松林中にあり。古くは塚であることを知る者はなかったが、狐塚と呼んで近づかなかった。明治8年、発掘調査を行う。多数の遺物出土あり。宮崎県庁に提出する。 |






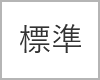
 閉じる
閉じる
更新日:2023年12月01日