仁王護国寺跡
仁王護国寺は、延暦元年(786)に天台宗の僧光喜坊快久が勅命を受けて鵜戸山大権現の別当寺として再興したものと伝えている。それ以前にも僧坊はあったとみられる。山号は鵜戸山または吾平山と称し、初め天台宗、後に真言宗となった。八丁坂下り階段の両側に、明治維新まで仁王護国寺の12の支院があった。
寺領は、431石余り、本末合わせて18ヶ寺を擁する両部神道の大道場で、日本三大権現の一つとして、又、西の高野としてその盛観を讃えられていたが、明治維新の神仏分離廃仏毀釈によって、或いは焼却せられ、或いは破壊せられ、或いは境外に運び去られて今は無昔の俤だになく徒に変遷の大なるを嘆ぜしめるのみである。
堂坊は廃止毀却され、仁王門は焼却された。辻の堂の本尊脇士は撤去されて今は吹毛井新墓地の入口にあり、本地堂観音は境外に撤去された。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 種類 | 寺跡 |
| 文化財指定等 | 未指定 |
| 指定年月日 | |
| 所在地(官報・文書等の記載) | 日南市大字宮浦 |
| 近隣集落・小字 | 宮浦 |
| 関連文化財群 | 鵜戸山信仰と日向神話 |
| 保存活用区域内 | 鵜戸山信仰と日向神話 |
| 出典 | (日向地誌) |
| 備考 | 真言宗。鵜戸山の東南の腹、平坦な所にあり。慶応3(1867)廃寺。 |






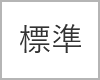
 閉じる
閉じる
更新日:2023年12月01日