榎原神社

榎原神社は飫肥藩主伊東祐久により鵜戸神宮を分祀して創建された神社で、鵜戸神宮とともに、歴代飫肥藩主からも崇敬されていた。また、縁結びの神として広く地域の信仰を集め大いに賑わった。榎原地区は、行政上「上講」、「中講」、「下講」、「札之尾」の4地区に分けられている。地区名にある「講」とは、宗教上・経済上の目的のもと結成された社会集団のことを意味しており、現在でも榎原神社への信仰があつい地域である。
寛永17年(1640)、鵜戸山仁王護国寺38世実融が、榎原の地福寺の僧であった精能とともに、鵜戸山大権現を分霊し、飫肥藩三代藩主伊東祐久によって万治元年(1658)に地福寺境内を社地として榎原大権現が創建された。一説には、神女と称された寿法院(万寿)の進言によると伝えられている。延宝2年(1674)には万寿の霊を祀る桜井大権現が造営され、榎原大権現とともに両権現と呼ばれて、歴代藩主以下、多くの人々の参詣が絶えなかった。飫肥藩では、鵜戸山に431石、榎原山に150石を寄附している(「県郷村社以下寺院」)。
榎原大権現には別当寺として貴雲山地福寺があったが、明治5年(1872)に廃寺となっている。現在の榎原神社境内に残る鐘楼は、天保13年(1842)に建立された。神仏習合の象徴的建物で、2階が鐘つき堂となっている。1階はなめらかな内湾曲線のまるで袴のような形をしており、1階と2階のバランスが見事に調和している建物である。また、本殿は、宝永4年(1704)に建立されたもので、正面から見ると権現造り風であるが横から見ると後ろ半分が八幡造り風になっている。これを八ツ棟造りと呼んでおり、鵜戸山大権現の本殿と造りが類似している。また楼門は、文化13年(1816)に建立されたもので、1階に屋根がない2階建の楼門造りの様式を持つ。楼門造りの門はおもに寺院に用いられることが多く、やはり神仏習合の象徴的建物であるといえる。門の両側に石で彫られた仁王像が配置してあり仁王門とも呼んだ。本殿、楼門、鐘楼は宮崎県指定文化財となっている。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 種類 | 神社 |
| 文化財指定等 | 未指定 |
| 指定年月日 | |
| 所在地(官報・文書等の記載) | 日南市南郷町榎原甲1134番地イ号 |
| 近隣集落・小字 | 榎原(上講) |
| 関連文化財群 | 榎原神社と門前町 |
| 保存活用区域内 | 榎原神社と門前町 |
| 出典 | 社寺調査 (日向地誌) |






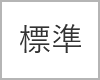
 閉じる
閉じる
更新日:2023年12月01日