飫肥杉

南九州の高温多湿な土地柄で育つ飫肥杉は、樹脂が多くて水を吸収することが少なく、弾力があって曲げに強く、比重が小さくて浮力があり、衝撃によって割れることの少ないことから、木造船の造船材として広く用いられていました。
江戸時代、飫肥藩(現在の日南市と宮崎市の一部)では、藩の殖産興業政策として領内の山々に飫肥杉の植林を推進しました。幕末にはこれらの杉が伐採期となり、瀬戸内海沿岸の造船地帯で、造船材としての飫肥杉弁甲が大量に取引されるようになりました。
明治時代から大正時代を経て、昭和40年代までは、西日本の木造船の大半は飫肥杉で造られました。
江戸時代には飫肥藩の専売品であった飫肥杉は、現在、宮崎県全体で植林されるようになり、宮崎県の県の木、日南市の市の木として、日南市のみならず、宮_を代表する地場産品となりました。平成3年度から現在まで、20年連続でスギ素材生産量日本一を誇っています。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 種類 | 生業 |
| 文化財指定等 | 未指定 |
| 所在地(官報・文書等の記載) | 日南市北郷 |
| 関連文化財群 | 飫肥街道と山仮屋関所 |
| 保存活用区域内 | 外 |
| 出典 | まちあるき |






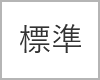
 閉じる
閉じる
更新日:2023年12月01日