松永のシイ

寛永13年(1636)、3代飫肥藩主伊東祐久は弟の伊東祐豊に、松永村と南方村(宮崎市)を添えて分家させ徳川家の旗本として出仕させた。
ところが、元禄2年(1689)祐豊の子、祐賢が幕府より蔵米取を命ぜられたため、松永村と南方村が幕府の直轄地(天領)に編入されてしまった。松永のシイはこの時に植えられたと地元で伝えられている。なおシイの近くには、古くから広渡川から水を引く松永用水の取り入れ口がある。松永用水は穀倉地帯である東郷地区を潤す重要な用水であった。
江戸時代中期の村絵図によると、シイのある上松永川鶴地区と佐土原堤沿が旗本交代寄合伊東氏領の上東弁分村飛地に編入されている。これは幕府直轄領の創設にともない、飫肥藩が松永堰と用水の管理権を確保するため松永村から分離して、その支配を代行したためである。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 種類 | 植物 |
| 文化財指定等 | 市指定 |
| 指定年月日 | 1970年11月3日 |
| 所在地(官報・文書等の記載) | 日南市大字松永3499番地 |
| 近隣集落・小字 | 松永 |
| 年代 | |
| 関連文化財群 | 外 |
| 保存活用区域内 | 伊東と島津の中世城郭群 |
| 出典 | 日南市指定文化財一覧 |






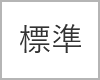
 閉じる
閉じる
更新日:2023年12月01日