定額減税補足給付金(不足額給付)について
【受付を終了しました】令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)
受付は令和7年10月31日で終了しました
定額減税補足給付金(不足額給付)の給付対象と思われる方に対し、7月中旬以降順次「支給のお知らせ」(緑色の用紙)、「支給確認書」(緑色の用紙)、「申請書」(黄色の用紙)のいずれかをお送りしています。
お手続きが必要な方で、まだ申請がお済みでない方は、受付期限までに申請してください。
また、書類が届かない方で、ご自身が給付対象と思われる方は、日南市福祉課給付金コールセンターまでお問合せください。
受付期限 令和7年10月31日(金曜日)当日消印有効
福祉課給付金コールセンター 0120-782-988(平日8時30分~17時15分)
物価高騰による支援のため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時給付金を活用し、令和6年度に実施した当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、本来給付すべき所要額と、当初調整給付所要額との間で差額が生じた方に、その差額を支給します。
支給対象者
原則として令和7年1月1日に日南市にお住まいの方(注1)で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方(令和7年1月1日に日南市にお住まいでない場合は、令和7年1月1日お住まいの市区町村にご確認ください。)
(注1)令和7年1月1日に日南市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付金が支給されます。
現時点で支給対象者に該当するかどうかは、お答えできませんので、ご了承ください。
不足額給付 1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付所要額との間で差額が生じた方。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
【対象となりうる例】
(例1)令和5年所得に比べて令和6年所得が減った場合

【解説】当初調整給付時点では、所得税における定額減税可能額30,000円、令和5年所得に基づく推計所得税額が20,000円であったため10,000円が当初調整給付所要額であった。令和6年所得が確定し、所得税額(実績)が減少したことで、定額減税可能額は30,000円で変わらないものの、所得税額が10,000円となり、不足額給付所要額は20,000円となった。不足額給付所要額から当初調整給付所要額を引いた10,000円が不足額給付として給付される。
(例2)令和5年に比べて令和6年の扶養の数が増えた場合

【解説】当初調整給付時点では、所得税における定額減税可能額は本人と扶養家族1人で60,000円、推計所得税額が50,000円であったため、10,000円が当初調整給付所要額であった。令和6年に扶養家族が1名増えたことで定額減税可能額が90,000円となり、令和6年所得税額(実績)は50,000円と変わらないため、不足額給付所要額は40,000円となった。不足額給付所要額から当初調整給付所要額を引いた30,000円が不足額給付額として給付される。
(例3)当初調整給付後に税額修正等により、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方
不足額給付 2
次の1~3の要件すべてを満たす方
- 本人として定額減税の対象外である方
令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円の方 - 扶養親族等として、定額減税の対象外である方
税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超)方 - 低所得世帯向け給付(注1)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
(注1)低所得世帯向け給付とは・・
- 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
- 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
【対象となりうる例】
(例1)
夫(個人事業主)妻(事業専従者)の世帯で、納税者である夫の個人商店を手伝う 事業専従者(配偶者控除・扶養控除の対象とならない)の妻であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)場合

【解説】納税者である個人事業主の事業専従者(個人事業主の配偶者)である妻は、自身の給与収入が50万円であり、所得税、住民税が非課税であるため定額減税の対象外である。また、税法上、事業専従者である妻は個人事業主である夫の扶養親族等にも含まれないため扶養親族としても定額減税の対象外である。さらに、世帯の中に課税者がいることで低所得世帯向け給付金の対象ともならなかったため、妻は不足額給付2の対象となる。
(例2)
父・息子(納税者)・息子の妻の世帯で、
公的年金収入が158万円(合計所得金額48万円)超、概ね170万円以下(所得税・住民税が課されない)の65歳以上の高齢者が、納税者である息子等と同居している場合

【解説】父の年金収入は165万円で、父本人の状況等により所得税・住民税(所得割)ともに非課税となったため、本人として定額減税の対象外である。また、合計所得金額が48万円を超えることで、息子の定額減税においても扶養親族等とならないため、扶養親族等としても定額減税の対象外である。さらに、納税者である息子等と同居していることで低所得世帯向け給付の対象ともならなかったため、父は不足額給付2の対象となる。
給付額
事務処理基準日(令和7年7月7日)時点に賦課処理が完了している課税資料をもとに算定します。
不足額給付 1


不足額給付時に算定した調整給付所要額が、令和6年に給付した「当初調整給付所要額」を上回る方に対して、当該上回る額を「不足額給付額」として給付します。不足額給付時、当初調整給付時ともに給付額は1万円単位に切り上げて算出します。ただし、不足額給付時に算出した調整給付所要額が当初調整給付所要額を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。
不足額給付 2
最大4万円
(注意)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
申請方法
要件を満たす可能性のある方へは、7月下旬以降順次「支給のおしらせ」「支給確認書」「申請書」のいずれかをお届けします。
- 「支給のお知らせ」が届いた方
原則、お手続きは不要です。ただし、支給口座の変更や支給辞退のご希望がある場合は「日南市福祉課給付金コールセンター」へ、下記期限までにご連絡ください。
口座の変更等なければ、8月上旬の支給を予定しております。
コールセンター 0120-782-988(受付時間)8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
ご連絡期限:令和7年7年31日(木曜日)17時15分まで - 「支給確認書」が届いた方
支給口座の申し出が必要です。郵送申請または電子申請でお手続きをお願いします。
申請受付後、内容に不備がなければ、2~3週間程度(注1)で指定口座へ振込みます。
(注1)申請開始直後は多数の返信が予想されるため、受付から振込まで2~3週間以上かかる場合があります。 - 「申請書」が届いた方
課税資料等をもとに、支給要件を満たす可能性がある方に送付しています。郵送申請、電子申請により手続きが必要です。申請書受付・審査後、「支給」「不支給」を決定します。 - 何も届かなかった方
ご自身でこの給付金の対象と思われる方で、8月下旬までに通知が届かなかった方は、コールセンターへご連絡ください。
申請期限
令和7年10月31日(金曜日)(消印有効)
原則、住所地に郵送します。都合により長期不在となる方はご注意ください。
コールセンター
日南市福祉課給付金コールセンター
電話番号:0120-782-988(受付時間)8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
現在、支給対象者の確認および給付額算定に向けて作業を進めているところです。そのため、具体的なお問い合わせ(対象者に該当するか否か・支給金額等)にはお答えできません。
所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご確認ください。
給付金を語った詐欺にご注意ください
現時点で、日南市からの定額減税に伴う不足額給付のお知らせは、当ホームページのみで掲載しています。メール・郵送で個別に連絡はしていません。「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。
日南市からは、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を教えてほしい、ということは絶対にありません。「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。給付金を騙った不審な電話や郵便物・メール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1163
ファックス番号:0987-31-0288
福祉課 管理係へのお問い合わせ




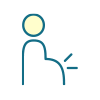

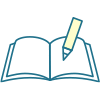
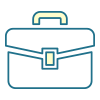
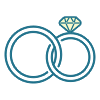

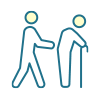
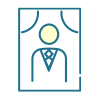







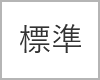
更新日:2025年11月01日