農業生産法人(農地所有適格法人)について
農業生産法人に関する改正のお知らせ
平成28年4月1日に施行された改正農地法において、農業の6次産業化を進めるため、農地の所有が認められている法人の要件である農業生産法人の呼称が農地所有適格法人になりました。
- 法律上の名称が農業生産法人から農地所有適格法人に変更となりました。(注意)ただし、名刺や看板、法人登記等に付けている「農業生産法人」という名称を変更する必要はありません。
- 構成員に占める農業者以外の割合も議決権の2分の1未満まで認めます。(今までは、4分の1以下でした。)
- 法人の役員等の農作業従事要件も1人以上が年間60日以上を従事すれば足りることとなりました。(その法人の常時従事者たる構成員が理事等の数の過半を占めていることは同じです。)
改正の概要
農業生産法人の見直し(平成28年4月1日) (PDFファイル: 626.9KB)
農業生産法人(農地所有適格法人)とは
農地法では、所有権も含めた農地の権利を耕作目的で取得できる法人として一定の要件を満たすものを「農地所有適格法人」と規定しています。(農地法第2条第3項)
1 農業生産法人(農地所有適格法人)として認められる組織形態
- 合同会社、合名会社、合資会社、株式会社(ただし、定款に株式の譲渡につき当該株式会社の承認を要する旨の記載あり)
- 農事組合法人(ただし、2号法人に限る)
2 事業要件
(1)主たる事業
法人の主たる事業は、農業、その行う農業に関連する事業、農業と併せて行う林業であることです。農業に関連する事業とは次のような事業を指します。
- 農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工
- 農畜産物の貯蔵、運搬又は販売
- 農業生産に必要な資材の製造
- 農作業の受託
- 農村滞在型余暇活動に利用されることを目的とする施設の設置及び運営並びに農村滞在型余暇活動を行う者を宿泊させることなど農村滞在型余暇活動に必要な役務の提供
(2)法人の構成員
その法人の組合員、株主、又は社員は、全て次に掲げる者のいずれかであること。
1.その法人に農地若しくは採草放牧地について所有権若しくは使用収益権を移転した個人又はその一般承継人
2.その法人に農地又は採草放牧地について使用収益権に基づく使用及び収益をさせている個人
3.その法人に使用及び収益をさせるため農地又は採草放牧地について所有権の移転又は使用収益権の設定若しくは移転に関し第3条第1項の許可を申請している個人
4.その法人の行う農業に常時従事する者(年間150日以上)
5.その法人に農作業の委託を行っている個人
6.その法人に基盤法第7条第3号に掲げる事業に係る現物出資を行った農地中間管理機構
7.地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組合連合会
8.その法人からその法人の事業に係る物資の提供若しくは役務の提供を受ける者又はその法人の事業の円滑化に寄与する者であって政令で定めるもの
9.その法人の理事等及び農林水産省令で定める使用人のうち1人以上が農林水産省令で定める日数以上農作業に従事すること。
(3)その他
1.議決権は、農業者以外の構成員の有する議決権等を総株主の議決権等の二分の一未満まで認められます。
3 報告・勧告・あっせん等
1.報告義務
農業生産法人(農地所有適格法人)は、毎年事業の状況その他農林水産省令で定める事項を農業委員会に報告しなければなりません。この農業生産法人(農地所有適格法人)が、法人でなくなった場合のその法人及びその一般承継人についても同様の報告義務があります。農業委員会への報告を怠った場合、あるいは虚偽の報告を行った場合には、30万円以下の過料に処することとされています。
4 農業生産法人(農地所有適格法人)の解散
1.農業委員会の是正指導や他の農業者への農地のあっせん等にかかわらず、なお、事態の改善が見込まれない場合には、その法人又はその一般承継人が所有する農地等や使用及び収益を目的とする権利を有する農地等については、一定の手続きを経て、国によって買収されることになります。
5 その他
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1148
ファックス番号:0987-24-0080
農業委員会事務局 農業委員会係へのお問い合わせ




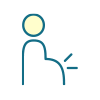

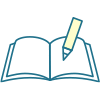
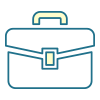
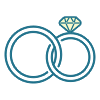

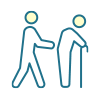
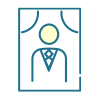







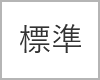
更新日:2023年12月01日