農業者年金のご案内
農業者の方なら 広く加入できます
国民年金の第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の人はだれでも加入できます。
農地を持っていない農業者、配偶者や後継者などの家族従事者も加入できます。脱退も自由です。脱退一時金は支給されませんが、加入期間にかかわらず、それまでに支払った保険料は、将来受給する年金の原資となります。旧制度(平成13年12月末日まで)の加入者で特例脱退した人も、60歳未満であれば加入できます。
(注意)農業者年金に加入される方は、国民年金の付加年金(付加年金保険料月額400円)への加入も必要となります。
積立方式で安定した年金制度です
自らが納めた保険料とその運用収入を,将来受給する年金の原資として積み立てていき、この年金の原資の額に応じて年金額が決まる積立方式(確定拠出型)の年金です。加入者や受給者の数に左右されることがなく、運用利回りの状況などで保険料が引き上げられることもない安定した年金制度です。
保険料などの資産運用は、農業者年金基金が一元的に行っており、国内債券を中心に複数の資産への分散投資を行うなど安全かつ効率的な運用を行っています。また、毎年6月末日までに「付利通知」で個人ごとの付利結果や年金原資の積立状況をお知らせします。
(注意)運用の結果得られる年金原資が、加入者が納付した保険料の総額を下回らないという保証はありません。そのため安全性の高い資産構成割合の採用や、65歳の年金裁定時に運用収入の累計額ができるだけマイナスとならないようにするための準備金の仕組み(付利準備金)等を導入しています。
終身年金で80歳までの保証付きです。
年金は生涯支給されます。仮に80歳到達月前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳到達月までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、死亡一時金として遺族(死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であり、死亡登記、死亡した者と生計を同じくしていた者)に支給されます。
保険料の額は自由に決められます
自分が必要とする年金額の目標に向けて、自分で保険料を決められます(通常加入は、月額2万円から6万7千円までの間で千円単位で変更可能)。農業経営の状況や老後設計に応じて、いつでも見直すことができます。また、翌年分を一括して支払う前納の仕組みもあります。令和4年1月1日から、35歳未満で認定農業者に該当しない等一定の要件を満たす方は、1万円からでも通常加入できるようになりました。
さらに 農業の担い手には保険料の国庫補助があります
認定農業者で青色申告をしているなど、農業の担い手となる方には、国から月額最高1万円の保険料補助があります。
1 保険料補助は通常の加入要件に加え、次の3つの要件を満たす方が受けられます
- 60歳までに保険料納付期間等が20年以上見込まれること。
- 必要経費などを控除した後の農業所得が900万円以下であること。
- 区分表の区分1から5の要件に該当する人
2 最長20年間の保険料補助が受けられます
保険料の補助が受けられる期間は、1.と2.の期間を通算して最長20年間(補助額は最高216万円)です。
- 35歳未満であれば要件を満たしているすべての期間
- 35歳以上であれば10年以内
3 国庫補助額も自分の年金として受け取れます
国庫補助額とその運用益は、個人ごとに積み立てられ、原則65歳から特例付加年金として受給できます。
ただし、特例付加年金を受給するには、農地等の経営継承が必要となります。経営継承の時期についての年齢制限はありません。自分で積み立てた分は、原則65歳から農業者老齢年金として受給することができますので、65歳からの農業者老齢年金を受給しながら農業を続け、本人の都合に応じて特例付加年金の受給時期を決めることができます。
(注意)ただし、保険料の国庫補助分については、特例付加年金として給付されるものとして、死亡一時金の支給はありません。
公的年金ならではの税制上の優遇措置があります
支払った保険料は、全額が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税の節税(支払った保険料の15~30%程度)につながります(民間の個人年金の場合は、控除額の上限は4万円(平成24年1月1日より前の保険契約については5万円)です)。また、保険料などの年金資産に対する運用益は非課税です。さらに、将来受け取る農業者年金は、公的年金等控除の対象となり、65歳以上の方であれば、公的年金等の合計額が110万円までは全額非課税となります。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1148
ファックス番号:0987-24-0080
農業委員会事務局 農業委員会係へのお問い合わせ




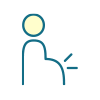

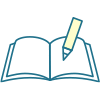
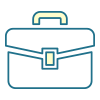
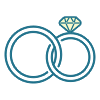

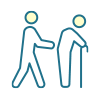
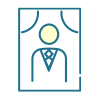







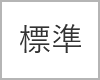
更新日:2023年12月01日