国民健康保険税について
問い合わせ
課税について
市民課保険係 電話番号:31-1126
納税について
税務課納税管理係 電話番号:31-1122
申告について
税務課市民税係 電話番号:31-1121
納税義務者について
被保険者である世帯主を、納税義務者として、課税します。
ただし、世帯主が職場の健康保険等に加入している場合であっても、家族の中に国民健康保険の加入者がいれば、納税義務者(擬制世帯主)となります。
国民健康保険税の決め方
日南市の国保税は、「世帯の所得に応じた所得割」、「世帯の資産に応じた資産割」、「世帯の加入者数に応じた均等割」、「一世帯当たりの平等割」の4方式で、4月から翌年3月までの1年間分を世帯ごとに計算した「医療給付費分」、「後期高齢者支援金分」、「介護納付金分」の合計額です。
| 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 |
|---|---|---|---|
| (前年中の所得額-基礎控除額43万円)×所得割税率 | 今年度の固定資産税額×資産割税率 | 国保加入者数×均等割税率 | 一世帯当たりの平等割税率 |
| 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 |
|---|---|---|---|
| (前年中の所得額-基礎控除額43万円)×所得割税率 | 今年度の固定資産税額×資産割税率 | 国保加入者数×均等割税率 | 一世帯当たりの平等割税率 |
| 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 |
|---|---|---|---|
| (前年中の所得額-基礎控除額43万円)×所得割税率 | 今年度の固定資産税額×資産割税率 | 国保加入者数×均等割税率 | 一世帯当たりの平等割税率 |
医療給付費分 + 後期高齢者支援金分 + 介護納付金分 = 1年分(4~3月分)の国民健康保険税
(注意) 税率については、毎年5月末に決定されます
所得の申告について
所得税や住民税が非課税の方、収入のない方も原則として申告が必要です。
申告をされないと、課税や給付で不利益を受けることがありますので、適正な申告をお願いします。
なお、納めた国民健康保険税は、全額が社会保険料の控除対象となりますので、確定申告書や年末調整のときに手続きしてください。(納付済確認書を市民課保険係で発行しています。)
国民健康保険税の軽減について
国民健康保険税には、低所得者の負担を軽減する制度があり、均等割と平等割が軽減されます。
世帯の合計所得と加入者数に応じて、それぞれ7割・5割・2割の軽減制度を受けることができます。
軽減を受けるための手続きは必要ありませんが、所得の申告をされていない(未申告)と基準に該当しているかどうか判断できないため、軽減の制度が適用されません。
国民健康保険税の激変緩和措置等について
- 一定の所得以下の方に対する軽減について
国民健康保険税の軽減を受けている世帯については、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移った後も、世帯の構成や収入の状況が変わらなければ、後期高齢者医療制度に移った年と同様に、保険税の軽減措置が受けられます - 世帯で賦課される保険税の軽減について
国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより単身世帯となる方については、保険税のうち平等割が、移行した月からその年度中及びその翌年度移行後5年間、2分の1が軽減され、さらに6年目以降3年間は4分の1が軽減されます。 - 被用者保険等の被扶養者だった方の保険税の軽減について
被用者保険等の被扶養者だった方(旧被扶養者)は、被保険者が後期高齢者医療制度に移行することに伴って、国民健康保険に加入すると、保険税を負担することになります。しかし、被用者保険等の被扶養者から国保被保険者となった65歳以上の方(旧被扶養者)については、当分の間次のような緩和措置があります。(ただし、均等割と平等割は資格取得から2年間のみ) - 旧被扶養者に係る所得割及び資産割は、賦課しません。
- 旧被扶養者に係る被保険者均等割額を半額とします。
- 旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割額を半額とします。
年度の途中で加入・脱退のときの国民健康保険税について
国民健康保険税は、加入等の手続きをした日からではなく、資格を取得した月から保険税が課税されます。また、年度途中からの加入・脱退については、月割で計算します。
国民健康保険税の納め方
普通徴収
納付書や口座振替により納めていただく方法です。納期は、原則として年10回で、6月から翌年3月までの毎月末日(月末が金融機関休業日のときは次の営業日)です。
口座振替の手続きについて
納税通知書、預金(貯金)通帳、通帳印をお持ちになり、市指定金融機関、ゆうちょ銀行等で手続きをしてください。
特別徴収
年6回、偶数月の年金支給日に年金から徴収する方法です。(年6回のうち、4・6・8月の3回は、「仮徴収」としてその年の2月に年金から差し引きした額と同額を差し引きすることになっています。)
特別徴収の対象者
世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯主(擬制世帯主を除く)で、年額18万円以上の年金を受給している人が特別徴収の対象となります。また、複数の年金を受給されている場合は、法令で定められた優先順位により徴収する年金が決まります。
ただし、年度途中で75歳になる世帯主や介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の2分の1を超える場合は、国民健康保険税は特別徴収しません。
(注意)特別徴収の対象者の方については、口座振替と特別徴収との選択ができます。詳しくは、市民課保険係にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1126
ファックス番号:0987-21-1083
市民課 保険係へのお問い合わせ




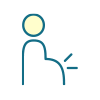

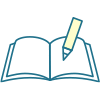
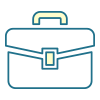
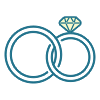

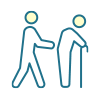
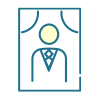







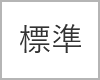
更新日:2025年04月01日