市指定文化財
歓楽寺の墓碑群

隈谷側沿いの中隈谷に位置する。南の山には新城跡があり、その山裾に約180基の板碑、五輪塔が残っている。銘が残っているもののうち、最も古いのは、正和4年(1315年)の板碑である。市内では、大迫寺石塔群とともに最も古い石塔群である。
振徳堂

天保2年(1831年)、藩主伊東祐相により、従来の小規模な学問所を増改築して設けられた藩校である。教授陣には、清武から安井滄洲、息軒親子を招き、本格的な藩校として開校した。
振徳堂からは、小倉処平や小村寿太郎を輩出している。昭和51年(1976年)、現在の姿に修復された。
鵜戸山別当墓地並びに墓

鵜戸神宮の参拝路である八丁坂の最高所に位置する。鵜戸神宮は明治以前は神仏習合であり、鵜戸山仁王護国寺はその別当寺で、住職が別当職を兼ねた。寺は、延暦5年(786年)に勅号を得て創建されたと伝えられ、墓地には関係者の墓が残る。
鵜戸山石灯籠のうち紙開発灯籠一対

産業開発の一政策として楮栽培及び紙の開発を計画した飫肥藩は、大阪の両替商油屋善兵衛から資金の提供を受け、飫肥藩内で和紙を生産、善兵衛が大阪で販売した。紙開発灯籠はこの事業の成功を祈念して天保3年(1832年)に善兵衛が鵜戸神宮に奉納したものである。
鵜戸山八丁坂

鵜戸山への参拝路として吹毛井の港から神宮の山門まで続く長さ約800メートル(八丁)の石段である。言い伝えによると、吹毛井に住む尼僧が頭に磯石をかついで築いたものという。
豫章館

明治2年(1869年)、版籍奉還により、飫肥第14代藩主伊東祐帰が知藩事に任命され、父祐相とともに飫肥城内より移り住んだ屋敷。それまでは、一門伊東主水の屋敷であった。豫章館の名は、祐相が邸内にあった樹齢数百年の大クスにちなんで名付けたものである。
商家資料館

明治3年(1870年)に山林業の山本五平が建てた建物で、飫肥杉の巨木を使った白漆喰の土蔵作りである。飫肥城下町は、慶応2年(1866年)の大火で全焼しており、その直後に建てられたこの建物は、本町では最も古い建物である。
飫肥城下町の本町通りは、商人町として栄えた。資料館は、往時の商家の様子を後世に残すため、昭和58年(1983年)に開館した。
願成就寺並びに山門

願成就寺は談義所とも呼ばれる真言宗の寺院である。現在の本堂は、飫肥藩十三代藩主伊東祐相が、天保3年(1832)に再建したものであると伝えられている。本堂は、桁行十間、梁行六間の六室取りであるが、現在は西に庫裡を設けている。本堂の建築材は飫肥杉の巨木を角材にして使用している。
山門は、飫肥藩内の武家屋敷にあった薬医門を移築したものであるという。なお、談義所は元来、飫肥城の鬼門を守るため創建された寺院で、伽藍は本堂・開山堂・護摩堂・経蔵・鐘楼・山門等で構成されていたという。
願成就寺石垣並びに石段

願成就寺は、当初飫肥城北の板敷の山腹にあって鬼門鎮護とされていた。しかし、この地が不便であったため、17世紀前半、現在の地に移転された。当時は真言宗寺院の飫肥領内本山であり、飫肥城下三大寺の一つとして藩から厚く処遇されていた。石垣並びに石段は、その格式の高さを偲ばせる。
旧伊東伝左衛門家

横馬場通りと八幡通りの交差した角地を占める武家屋敷である。建築様式から19世紀の建築であると推定される。
昭和60年(1985年)に日南信用金庫から市に寄付を受けた際、屋根や内装を修理した。修理の際、屋根は茅葺きであったことが判明したが、維持管理の必要から修理前の瓦葺を踏襲した。
旧山本猪平家

飫肥の豪商山本猪平が、明治40年代に隣接する小村寿太郎生家が没落した際、寿太郎の父から土地を買い取って自宅を新築した建物である。その後昭和4年(1929年)、南に主屋を増築した他は、大きな増築や改築はなく、ほぼ建築当初の姿をとどめている。
一里塚標
一里塚は、江戸時代に距離の目安として1里(約4キロメートル)ごとに街道の両側に築いた塚のことである。この一里塚標は石柱で、飫肥城下から内之田まで1里であることを示している。明治中期には、地元の個人宅に移設されていた。現在は、歓楽寺境内に仮移設されている。
六地蔵幢

潮嶽神社から南に約100メートルにある、宿野墓地内にある六地蔵幢。天文9年(1540年)庚子八月の銘がある。
首洗い井戸組石

江戸時代、内之田の処刑場で、飫肥藩の重罪人の処刑が行われた。飫肥藩牢内での処刑は、武士は切腹、軽罪の者は絞殺、重罪人は、城下引き回しの上で内之田処刑場で斬罪に処せられた。木柵、矢来に囲まれた処刑場には、役人の控番小屋があり、砂利敷の小庭を通って処刑台場に向かった罪人の斬殺の後に役人がこの首洗い井戸で首を洗ったと伝えられる。
この処刑場は、明治維新後に廃され、処刑人の菩提を弔うためにその跡地は、歓楽寺に供養地として寺有とされていた。戦後、個人所有の農地となり、現在は整地されて水田となっている。この水田の畦に、処刑場首洗井戸の組石が3個残る。
板碑

下大藤折生田墓地にあり、3つに折れている。「□応六?巳二十七孝子等敬白」の銘文があり、正応6年(1293年)(永仁元年)のものと考えられる。
五輪塔

五輪塔は、卒塔婆の一つで下方から基礎・塔身・笠・請花・宝珠の五輪を積み上げ、地・水・火・風・空を表している。密教に由来するもので、平安中期頃から見られる。
この五輪塔は、空輪が亡失しているが、大きく立派である。銘文は無い。
水垂観音
水垂観音は、旧飫肥街道の内之田越えにあり、昔から地域住民尊崇の観音である。古老の口伝によれば、この水垂観音は明治初期までは境内も広く、堂は荘厳な観音造りで、殊に朱塗りの堂は巨松、奇石、石仏、石塔の並ぶ中に四囲の緑と白瀑に映えていたが、明治初年の山崩れで埋まり、境内は大きく変化し、昔を偲ぶ面影が無くなった。大正期に、本尊は盗難にあい紛失した。現在は、子持観音が祀られている。
(「北郷町文化財紀要第二集」)
海田家住宅

明治初めの建物と考えられる住宅である。この住宅は、江戸時代の形態を継承し、格式ある造りとなっている。
敷地には、主屋、納屋、馬屋兼納屋が3棟コの字型に並び、前庭を囲んでいる。主屋の棟は南北に配され、東側が玄関、その先が前庭である。主屋の西側は1段高くなっており、自然の地形をうまく利用し、わずかの敷地に3棟を配置させている。
長持寺の勅額

江戸時代の長持寺は、飫肥城の北方、原之迫にあった曹洞宗寺院であり、飫肥城下三大寺院の一つであった。創建は古く、応永33年(1436年)である。
天文11年(1542年)、開基光訓禅師の百回忌が行われ、伊東義祐が朝廷に奉じて後奈良天皇から「勅賜長持寺禅寺」の勅額を賜った。その後、長持寺は飫肥藩の成立により原之迫に再興され、勅額は山門に掲げられた。現在は、願成就寺に保管されている。
鵜戸山の磨崖仏

鵜戸山仁王護国寺の第47世別当がその在任中の明和元年(1764年)、同2年(1765年)に仏師延寿院に彫刻させたものであり、八丁坂近くの岩壁に閻魔大王、四天王像が彫ってある。往時は、護摩堂も建立してあり、鵜戸山修験者の道場であったと考えられる。
木造地蔵菩薩像
潮嶽神社に安置されている木像で、約55センチメートル。権現(神宮寺)のころの仏像である。
(「北郷町文化財紀要第一集」)
金銅製不動明王像
潮嶽神社に安置されている金仏で約10センチメートル。五大明王の一つで怒りの相を現し、右手に剣、左手に縄を持って、火災を背に座り、悪魔を降伏されるもの。権現(神宮寺)の頃の仏像である。
(「北郷町文化財紀要第一集」)
石地蔵菩薩
伝承によれば、飫肥藩主伊東氏が高僧の請を受けて処刑者の霊を弔い供養するために、彫師を招いて彫らせたものだという。
昭和14年の大洪水により松永橋近くに流され、現在地に仮住されている。坐高140センチメートル、頭廻り110.2センチメートル、肩巾55センチメートル。蓮華の上に坐した半跏像。
この五輪塔は、空輪が亡失しているが、大きく立派である。銘文は無い。
(「北郷町文化財紀要第一集」)
阿弥陀如来像

歓楽寺の本尊。木彫、金箔、漆塗像。高さ52センチメートル。年代は不明。光背は、明治17年(1884年)歓楽寺再建移転時に付背したもの。
(「北郷町文化財紀要第一集」)
木造阿弥陀如来立像及び木造薬師如来立像
薬師如来立像と釈迦如来立像は、台座背面に「天正十年」「上原長渡守」の墨書がある。光背は二体とも紛失してるが、共に一木造で本体の保存状態も良く、仏教美術史研究において資料的価値がある。
歓楽寺の香炉及び厨子

内之田の歓楽寺所蔵の仏具。歓楽寺は、真宗本願寺派の寺で、本尊は阿弥陀如来。厨子は、本尊がおさめられていたもので、外黒内朱の漆塗りで、解体されている。
(「北郷町文化財概要」)
松永観音堂鰐口
松永観音堂の鰐口は、松永の外山一族の墓地横に立つ観音堂に掲げられていた。
鰐口は青銅製で、直径15.6センチメートル、厚さ6.0センチメートル、鐘座6.6センチメートルを測る。表面には、「阿弥陀寺之鎮守之鰐口 應永十年癸未八月日」と刻まれた銘文がある。
伊東家及び浅野家女乗物

伊東家女乗物は、輿、轅ともに木製の黒漆塗で金蒔絵が施されている。全面に伊東家の家紋である庵木瓜、月星九曜紋があしらわれ、その間を桐唐草文でつないでいる。漆工技術はその当時の水準を示し、資料的な価値が高い。
浅野家女乗物は、輿、轅ともに木製で、黒漆塗、金蒔絵で鷹羽紋が散らされ、その間を金蒔絵、銀蒔絵の桐唐草文でつないでいる。伊東家11代祐民のとき、芸州浅野家より栄松院(為姫)が輿入れした際に乗用したもので、製作年代が推定できる大名家の女乗物である。漆工技術の水準からみても、歴史的、資料的価値は高い。
神楽面10面(郷原神社)
寛文・延宝年間の作で、10面のうち一番から八番までは連番でまとまって伝存している。神楽面の研究において、学術的価値のある資料となるものである。
四半的

射場から的まで四間半、弓矢とも四尺五寸、的が四寸五分で、すべて四半であることから四半的と呼ぶ。その起源は不詳であるが、戦国時代の宮崎城主上井覚兼の日記には「四半」の文字がみえる。
昭和初期に途絶えたが、第二次大戦後に復活して日南市を中心に娯楽競技として普及している。
御神子舞
舞の始めは、神武朝と伝えられる。神武天皇が東征前、潮嶽の里に火闌降尊(大伯父)へお別れのためお立ち寄りの折り歌を詠まれ、その歌にあわせて里の娘が舞ったという。
春秋の例祭に氏子の娘4名が選ばれ、晴衣の上に緋袴舞衣を着け、右手に榊、左手に末広(扇子)を持ち、神主の歌・太鼓に合わせて、静かに舞う清楚な舞である。
(「北郷町文化財紀要第一集」)
獅子舞
潮嶽に伝来の芸能で、海幸彦、山幸彦の争いのあと「これより後われ宮門を守らん」との仰せにより、以後ご巡幸の守護先守の姿を現すとも、また社宮門の守り獅子がいつの時代からか浜下り神幸の先守り役として舞い始めたとも伝えられる。
男獅子、女獅子の対をもって組み、太鼓、横笛、手拍子に合わせて藤の如く規則正しく前後左右に舞う勇壮絢爛な舞である。
(「北郷町文化財紀要第一集」)
棒踊り
海幸彦・山幸彦の争いの時、満潮の時今の潮嶽の里に着き給い、御弟の命に三種の神器を授け、「今より後吾将に汝命の俳優の民となり、宮門を守るに棒を以て仕え奉る」と仰せられたのに始まると言い伝えられる。
白かすりに、袴を着け、白足袋、草鞋、白鉢巻、白襷、後ろに五色の帯をたれ、3尺と6尺の棒で踊る勇壮活発な踊りである。
(「北郷町文化財紀要第一集」)
大塚古墳

潮嶽神社から西へ約1キロメートル、谷合地区の自然の山嶺を利用した古式古墳である。周囲約450メートル、縦170メートル、横85メートル。
潮嶽神社の祭神火闌降尊(ホノスセリノミコト)の陵と言い伝えられる。
(「北郷町文化財紀要第一集」)
妙満寺跡
郷之原伊十川にあり、現在は畑地。殉教蟄居の処の石碑が3つある。
(「北郷町文化財紀要第一集」)
経塚
曽和田茶園内にある。
(「北郷町文化財紀要第一集」)
郷之原城跡

郷之原城は、一名石崎城ともいい、大字郷之原字古城にあった。
日向地誌の記述から推して、郷之原城は南北朝時代には既に存在し、北郷石崎城(郷之原城)に立てこもる宮方(南朝)と武家方(北朝)の土持頼宣とが激しい戦いをし、武家方の土持頼宣が北郷石崎城を攻め落としたことがうかがえる。
(「北郷町文化財概要」)
山仮屋関所跡

関所跡は山仮屋地域、県道宮崎北郷線の上方にある。昔の往還(飫肥街道)は、上郷の花立から山頂を横断し、和当地・赤木を経て清武に通じ、飫肥を結ぶ要路であり、関所として最適の場所である。この道路は、文献によれば、天正から慶長の頃に開削されたという。
山仮屋関所は、寛文3年(1663年)以前に存在したものと思われ、その後は番所と名を変えて13戸の番卒をおき、江戸参勤交代の節には殿様の行列を整えたり、休憩所となって食事等の世話をしたと同時に、昼夜の別なく往来の人馬を監視し、旅人を調べる面番所でもあった。
(「北郷町文化財紀要第二集」)
脇本焼窯跡

酒谷の横山宝蔵氏が長崎県より陶工中里音吉ほか数家族20数人を招き、磁器を焼成するために作られた。特に盛んに生産されたのは明治30年前後の10年間で、脇本焼と名付けられた。
脇本焼は、白磁に青絵付されたものが主体であるが、青磁や透かし彫りの香炉などもある。
飫肥城跡

飫肥城は、広渡川の上流である酒谷川が大きく蛇行した小盆地に突き出た丘陵上に築城されている。中世には島津氏と伊東氏の抗争の舞台であり、近世には飫肥藩伊東家の居城として、日向を代表する城であった。その縄張りは、シラス台地を空堀で区切った壮大な規模のもので、各曲輪の独立性の高さが特徴となっている。
現在の石垣の大半は、貞享3年(1686年)から元禄6年(1693年)の大普請によって改修されたものである。
伊東家累代墓地

飫肥城下町を取り巻く酒谷川を西へ渡ったところの旧報恩寺(現在の五百?神社)にある墓地である。墓地内には、三位入道(伊東義祐)をはじめ、飫肥藩初代藩主伊東祐兵以下歴代藩主の墓がある。
昭和初期に途絶えたが、第二次大戦後に復活して日南市を中心に娯楽競技として普及している。
猪八重滝群
猪八重滝群には、五重の滝、岩見の滝、岩つぼの滝、瀬戸の滝、流合の滝、八とどろの滝、岩屋の滝など大小様々な滝がある。
また、この滝群はコケの宝庫である。コケ博士と言われる服部新佐らの調査研究により、様々なコケの群生が発見され、学界の注目を集める。
(「北郷町文化財概要」)
豫章館庭園

豫章館の南面に広がる庭園で、規模や手入れの良さでは、九州でも有数のものである。庭園は、広い空間のほぼ中央につるべ井戸を置き、井戸に向かう飛石が左右に分かれる二人組の法をとっている。庭園史上、武学流と呼ばれる作庭である。
八幡神社境内のクス

天正16年(1588年)、伊東祐兵が飫肥に入城して伊東家を再興した際、その記念として祐兵が手植えしたと伝えられるクスである。推定樹齢は約400年、樹高30メートル、幹周9.2メートルにもなる。
松永のシイ

元禄2年(1689年)、松永村と南方村(現在の宮崎市)を分けられて分家し、徳川家の旗本として出仕した伊東祐豊の子祐賢が、幕府より蔵米取を命じられたため、松永村と南方村は幕府の直轄地(天領)に編入されてしまった。松永のシイは、この時に植えられたと地元で伝えられている。
願成就寺のモクセイ

願成就寺は、飫肥藩の飫肥城改築に伴って17世紀中頃までに現在地に移転された。モクセイは、この今町移転に伴って植えられたと伝えられ、推定樹齢は300年である。
モクセイは、ギンモクセイの変種ウスギモクセイで、この種の樹木でこれほど巨大なものは県内でも珍しい。花は淡い黄色で香気が高く、秋の風物詩の一つとなっている。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1145
ファックス番号:0987-24-0987
生涯学習課 文化財係へのお問い合わせ




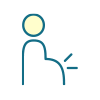

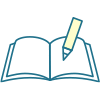
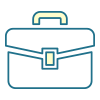
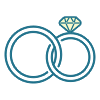

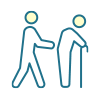
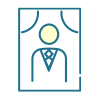







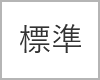
更新日:2024年01月30日