農地の貸借契約の解約について

農地の貸借(貸し借り)契約の解約について手続きをご案内します。
農地法第3条契約に基づく貸借契約の解約について(農地法第18条)
農地又は採草放牧地について売買等により所有権を移転し、又は賃借権その他の使用収益権を設定し、もしくは移転しようとする場合には、農業委員会の許可が必要となります。この許可を受けないでした所有権の移転等は効力を生じません。
一方、この貸借契約の解除も、耕作者の権利保護と地位の安定を図るため、原則都道府県知事の許可がなければ解約できないことを規定しています。さらに、賃貸借期間の定めのある場合は、通常、その期間の満了する1年から6ヶ月前までの間に相手方に賃貸借の更新をしない旨の通知をしない限り、従前の賃貸借と同一の条件で賃貸借をしたものとみなされます。(農地法第17条) → 法定更新となります。
合意解約の場合(許可を要さない解約となります。)
借り手と貸し手の双方が合意された解約である場合、解約によって農地等を貸し手に引き渡すこととなる期限前6ヶ月以内に成立した合意であることが合意書(賃貸借契約合意解約書、使用貸借契約合意解約書)により明らかな場合は、通知書(農地法第18条第6項通知書)により農業委員会へ届ければ、都道府県知事の許可を要しません。
使用貸借契約合意解約書 (Wordファイル: 33.5KB)
農地法第18条第6項通知書 (Wordファイル: 50.0KB)
次のような場合は、許可を要しません。(農地法第18条第1項ただし書き)
- 解約の申入れ、合意による解約又は賃貸借の更新をしない旨の通知が、信託事業に係る信託財産につき行われる場合
- 合意による解除が、その解約によって農地若しくは採草放牧地を引き渡すこととなる期限前6月以内に成立した合意でその旨が書面において明らかであるものに基づいて行われる場合又は民事調停法による農事調停によって行われる場合
- 10年以上の期間の定めのある賃貸借(解約権を保留しているものを除く)について更新拒絶の通知が行われる場合
- 水田裏作を目的とする賃貸借につき行われる場合
- 農地法第3条第3項の適用を受け同条第1項の許可を受けて設定された解除条件付き賃貸借で、当該農地を適正に利用していないため、あらかじめ農業委員会に届け出て解除される場合
- 農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画によって設定された解除条件付き賃貸借で、当該農地を適正に利用していないため、あらかじめ農業委員会に届け出て解除される場合
- 農地中間管理機構が農地中間管理法第2条第3項第1号に掲げる業務の実施により借受け、又は同項第2号に掲げる業務の実施により貸付けた農地等に係る賃貸借の解除が、同法の規定により都道府県知事の承認を受けて行われる場合
農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画による貸借契約の解除について
農業経営基盤強化促進法(以下「基盤法」という)に基づく農用地利用集積計画により農地の利用権設定や移転ができます。ただし、この制度で借り手となる者は一定の要件を満たした農業者であることが条件となります。基盤法では、契約期間が満了した場合法定更新とならず、貸借契約は終了します。ただし、契約期間の途中で契約を解約する場合は、農業委員会の決定を経て、農用地利用集積計画のうち当該賃借権又は使用貸借による権利の設定に係る部分を取り消さなければならない場合があります。解約にあたっては、日南市長へ合意解約届(合意解約届(賃貸借・使用貸借)基盤法)を提出してください。合意解約の書類として合意書(賃貸借契約合意解約書、使用貸借契約合意解約書)と通知書(農地法第18条第6項通知書)も必要となります。
合意解約届(賃貸借・使用貸借)基盤法 (Wordファイル: 32.5KB)
使用貸借契約合意解約書 (Wordファイル: 33.5KB)
農地法第18条第6項通知書 (Wordファイル: 50.0KB)
自動的に期間満了により解約される場合
農地等の賃貸借についての存続期間の満了は、農地法第17条の法定更新の規定との関係により一般的には賃貸借の終了事由とはなりませんが、例外的に次の場合は賃貸借の終了事由となります。 → 民法の原則に従って、存続期間が満了したときは、その時に自動的に終了します。
- 存続期間が1年未満の水田裏作を目的とする賃貸借
- 農地法の規定によって設定された農地中間管理権の賃貸借
- 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画によって設定又は移転された賃借権に係る賃貸借
- 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用配分計画によって設定又は移転された賃借権に係る賃貸借
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1148
ファックス番号:0987-24-0080
農業委員会事務局 農業委員会係へのお問い合わせ




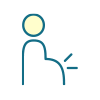

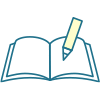
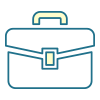
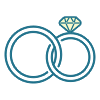

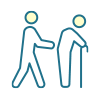
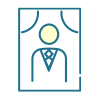







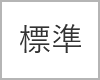
更新日:2023年12月01日