県指定文化財
大迫寺跡石塔群

鎌倉時代以降の寺院墓地と推定される。多宝塔、五輪塔、板碑など250基以上の石碑、石塔からなる。年代の判明するもので最も古いのは、永仁3(1295)年の板碑である。その他、鎌倉、室町、江戸時代の墓碑群がある。これらは、寺院周辺に散在していたものを、荒廃が著しいため現在地に集められたものである。
榎原神社鐘楼

天保13(1842)年に建立された。神仏習合の象徴的建物で、2階が鐘つき堂となっている。1階はなめらかな内湾曲線のまるで袴のような形をしており、袴腰と呼ぶ。この1階と2階のバランスが見事に調和している建物である。
榎原神社本殿(石の間拝殿を含む)

榎原神社は、万治元(1658)年に飫肥藩藩主伊東祐久によって創建された。本殿は、宝永4(1704)年に建立された。正面から見ると権現造り風であるが、横から見ると後ろ半分が八幡造り風になっている。これを八棟造りと呼ぶ。鵜戸山大権現の本殿と造りが類似している。また、出鼻の龍やバクなどの細工も技巧をこらしている。
鵜戸神宮本殿

鵜戸崎の日向灘に面した岩屋内に建てられている。本殿創建年代は諸説あり、詳細は不明である。「日向地誌」には長禄3(1459)年に後花園天皇が勅使を派遣して岩屋を見聞させたと記されている。
現在の本殿は、正徳元(1711)年に五代飫肥藩主伊東祐実が改築したものを明治22(1889)年に大改修し、その後昭和43(1968)年、平成8(1996)年にも改修が行われた。このように幾度の改修を実施したものの、権現造りの様式は往時のままであり、その文化的価値は高い。
山仮屋隧道

北河内にある、煉瓦巻きの道路トンネル。明治24年着工、明治25年完成。宮崎飫肥間を結ぶ県道開設に伴い建設された。
トンネル内で使用されている煉瓦は、大阪の堺から取り寄せた良質のもので、側壁部にはイギリス式の手法、アーチ部には長手積みの手法が採用されている。
トンネルは、内部の高さ約4.3メートル、トンネル幅約4.8メートル、道路幅員約3.8メートル、長さ約56メートル。
榎原神社楼門
文化13(1816)年に建立された。1階に屋根のない2階建ての門の造りの楼門造りである。楼門造りの門は、主に寺院に用いられることが多く、神仏習合の象徴的建物といえる。門の両側には、石で彫られた仁王像が配置してあり、別名仁王門という。1階と2階の高さの比が1対1で近世の建築の特徴が現れている。
泰平踊

飫肥城下町に江戸時代から伝わる踊りで、初め町衆によって踊られていた盆踊りである。宝永4(1707)年、対立関係にあった薩摩藩との和解が成立すると、藩はこれを祝って城下三郷の武士にも盆踊りへの参加を許した。これが泰平踊の起源である。
しかし、幕末の動乱期に再び武士の参加が禁じられ、その後中断していた。明治中頃に本町と今町で復活してからは、機会あるごとに踊られている。
田ノ上八幡神社の弥五郎人形行事

田ノ上八幡神社(飫肥板敷)において、「弥五郎様」と呼ばれる巨大な人形を作り、祭礼行列の先導役として引き出す行事である。
弥五郎様」は、昔、稲積弥五郎という巨人がこの地に八幡様のご神体を背負ってきたと伝えられている。毎年11月23日の秋祭りに登場する高さ7メートルに及ぶ人形は、白い髭のある朱面と烏帽子をつけ、朱の衣に袴をはかせ、腰に長刀右手に槍をもつ姿に組み立てられる。
都城市山之口町と曽於市大隅町にも同様の人形行事が伝承されている。
南郷村古墳
外浦古墳
年代は不詳である。潟上川の右岸にあり、石棺は地上にむき出しになっている。
潟上第1号墳
年代は不詳である。現在、墓地になっており全体の形も不明である。現在頂上部に石棺が残っている。
三本松古墳
霧島山の山頂にある円墳。年代は不詳。現在は二重になっており、上部の直径は12メートル、下部の直径は21メートル。頂上部にほこらがあり、神聖な場所として地区の人々が守っている。
東郷古墳
風田の日向灘に面した高さ61メートルの丘陵上にある古墳である。5世紀代の築造と思われるが、石室はすでに盗掘されており、竪穴系の石室と横口式の石室が直行して開口している。
細田古墳
大堂津海岸から2キロメートル上流の細田川左岸の自然丘陵上に築かれた古墳である。石室の形態から5世紀代の築造と考えられるが、すでに盗掘されている。
平成2年の調査の結果、自然丘陵の岩盤を掘り込んだ南北方向の長さ4.8メートル、幅1メートルの竪穴式石室が確認された。
狐塚古墳

風田に築かれた古墳である。この古墳の存在は古くから知られており、明治8(1875)年には発掘され、遺物も出土している。
平成6(1994)年の調査の結果、この古墳は横穴式石室を有する古墳時代終末期(7世紀初め)としては日本の最南端に位置する古墳であることが判明した。羨道の一部や天井部は原形を留めていなかったが、出土品は、馬具や武具、勾玉や切子玉などの装飾品、須恵器など多岐にわたる副葬品が出土した。特に金銅製装飾大刀、金銅製馬具、銅椀などは貴重な発見であった。
なお、横穴式石室の玄室規模では、宮崎県内最大規模のものである。
勝目氏庭園

飫肥城下の前鶴通りに面した30坪余りの庭園である。中国宋時代の玉潤が描いた山水画を模した「玉澗式」庭園といわれ、庭に配置した石で山水をあらわしている。江戸中期以降の様式をとる。
庭園を含む屋敷地は、承応年間(1652~54年)に鈴木猪右衛門、天保12(1841)年頃には藩医の一人である木脇隆敬が居住していた。
鵜戸千畳敷奇岩

鵜戸神宮の鎮座する鵜戸崎の南面にある。今から約1200万年前から600万年前にかけて堆積した地層(砂岩と泥岩の互層)が、傾いて日向灘に面しており、長い年月をかけて波に浸食され、現在の姿になった。こうしてできた波状岩は別名「鬼の洗濯板」(正しくは、隆起海床と奇形波蝕痕)と呼ばれ、とりわけ鵜戸千畳敷奇岩はその広さから県指定の文化財となった。
飫肥のウスギモクセイ
飫肥城西方の大字吉野方にある。指定時の大きさは、高さ12メートル、目の高さでの周囲1.85メートル、被覆面積25.5平方メートルに達していたが、昭和26年の台風により、高さ7メートルとなり往年の面影はない。樹齢は約400年を経ているものと思われる。
アカウミガメ及びその産卵地

絶滅危惧種にも指定されているアカウミガメ日南市内の海岸に、毎年産卵のために上陸している。なかでも風田・平山海岸に多くのアカウミガメが上陸することから、産卵地として指定、保護している。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1145
ファックス番号:0987-24-0987
生涯学習課 文化財係へのお問い合わせ




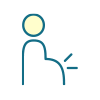

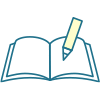
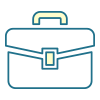
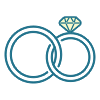

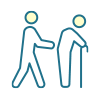
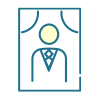







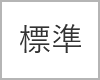
更新日:2023年12月01日